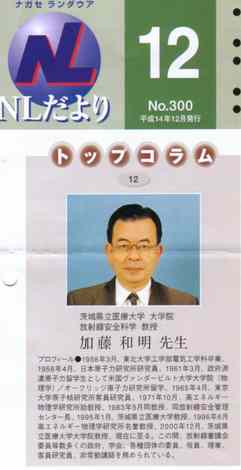 |
私の教育原理 筆者には今日の情況はつまぴらかでないが、大学卒業時の知識に照らすと、小・中・高校で教鞭を執るには教師の免状が必要であり、そのためには教育原理の授業を受けて単位を取得しなければならないことになっている。この”足伽”(?)は、大学や大学院で教鞭を執るものには課せられていない。見方に依れば大学/大学院の教師というのは就くのが最も容易な職業である。そんなわけで、筆者も大学教師として生計を立てている。奉職先に限ったことではないが、授業の上手い教師もいればそうでないのもいる。しかし、教育原理を履修しているかいないかは、授業の巧拙にあまり関係はないように見える。連れ合いの父親の専門がいわゆる教育学で、結婚した頃には某国立大学で教育学部長を務めていた。書斎に教育原理と題した書物があったので覗いてみたことがある。中身については殆ど記憶に残っていない。40年近く時間が経ってしまった所為もあるかも知れないが、よほど印象が薄かったのであろう。今恩い起こすことができるのは、「僕の教育原理は”学問の面白さを教えることです”」と、岳父である、この教育の専門家に向かって生意気に言い放ったコトだけである。彼はニコニコ間いているだけだった。 私のこの教育原理は今も変わっていない。24年余在職した前の職場での官職名は「文部教官」であった。教育者の端くれだったのである。実際に面倒見た学生は京都大学と東北大学から委託を受けた博士課程の学生2名だけであったが、あちこちの大学で非常勤講師を頼まれたので、教壇に立つ機会は少なからずにあった。純粋に教師業をやっているのは7年半前からであるが、実は、最初の就職先でも「原子炉研修所」という名の学校で授業を持たされていたことがある。この問、私の教育原理は一貫して上記のものであった。人間、年を取るにつれ頑固になるようなので、多分死ぬまで私の教育原理は変わらないものと思われる。 分析して考えて見ると、この考えは、勉強というものの本質は独学にあるとの信念に由来する。最近の学生は、試験のできが悪かったりすると、先生の教え方が悪いのだといって文句を付けに来たりする。何かを調べさせても、intemetで調べたけど出てきませんでした、などと嘯いている。すべてに受け身で頭を使おうとしない。行動の指導原理はメダカのそれと変わらない。大勢の流れに身を委ねるだけである。群れて行動することが個体や種にとってのリスクを低減化する一つの方法であるというのは、我々の先祖が長い時間掛けてDNAに刷り込んできた経験的な知恵なのだから、本能の命に従うことを行動の指導原理としている若者達には違和感がないのである。自分の頭で考える力を身に付けざせ、分かるということは納得することだと教えこまなければ、この国は滅んでしまうのではないだろうか。行き着く先が「ハーメルンの笛吹き」とならないことを祈るばかりである。 (茨城県立医療大学) 放射線教育フォーラム理事 加籐和明 |