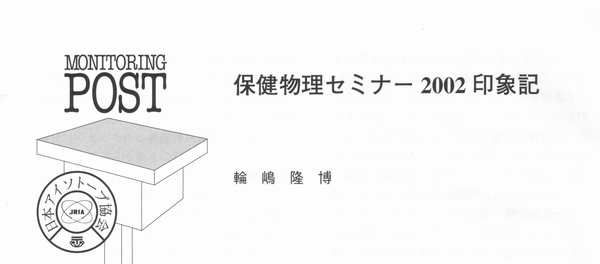 |
セミナーの概要 20年にわたる歴史をもつ「kumatoriサマーセミナー」を引き継ぎ,保健物埋セミナーと名を変えたこの研究会は,2002年は神戸で開催され(9月30日一10月l日),保健物理・放射線管埋関係者約200名の参加があった。今回のセミナーは自然放射線の規制,人工的に高められた自然放射線の規制の問題,これらを放射線審議会の答申に向けていかに取り組んでいくかという課題があり,また最近の原子力業界の不祥事への対応など,主催者側の方向性が感じられた。この趣旨にそった7つのテーマに20名の講演者,コメンテーターがそれぞれの立場から意見を述べられた。以下,プログラムの概要である。 テーマ1放射線関連法令について ①規制免除レベルについて 小佐古敏荘(東大原子力総合センター) ②電離則における放射線管理について 槙野順三(厚生労働省安全衛生部) テーマ2自然放射線源(NORM)からの被ばく ①ラドンによる被ばく 石川徹夫(放医研) ②地殻ガンマ線による被ばく 長岡鋭(原研) ③航空機での被ばく 藤高和信(放医研) ④自然放射性物質による被ばく モザナイトに着目して) 杉浦紳之(東大原子力総合センター) テーマ3ボイリングディスカッション 2030年には原子力技術者を確保できるか 吉川進(東京電力(株)) テーマ4ほどほどは健康のもと コメンテーター 金子正人(放射線影響協会) ①適量の放射線は健康に良い有力な証拠 近藤宗平(阪大名誉教授) ②適量の酒は健康に良い 一タバコは一 滝澤行雄(秋田大名誉教授) ③ラドンで関節炎を治そう 青山喬(滋賀医大名誉教授) テーマ5最近の放射線事故について コーディネーター 飯田孝夫(名古屋大院) く最近の事例報告について> 石田正美(文部科学省原子力安全謀) ①大蔵病院加速器被ばく事故 正木英一(同立成育医療センター) ②身元不明線源による事故 甲斐倫明(大分看護科学大学) ③非密封線源事業所のトラプル 川上猛雄(日本Rl実験支援機構) ④放射線事故と報道 加藤和明 (茨城県立医療大) テーマ6放射線管理者の認定について 座長 占部逸正(福山大学工学部) 宮部賢次郎(核燃料サイクル開発機構) 鈴木晃(東京電刀(株)) 征矢郁郎(三菱重工業(株)) 中里一久(慶応大医学部) 鈴木征四郎(原電事業(株)) 講演,討論の印象 再び保健物理学とは・・・・ 保健物理学とは,人体への放射線の健康影響に関して科学的な立場で明らかにし,またそれをいかに社会に適応させるか,という大変に裾野の広い学間であると私は認識している。参加者の専門分野は生物学・物理学・医学・原子力・放射線関運業界・行政ほか多彩である。本セミナーに参加することによって,その裾野の広さを実感でき,携わる環境の遠いのなかで相互の意見の交流が可能であるから,放射線関係者にはぜひ参加をお奨めしたい。 保健物理学での重要な議論の変遷をみると,「現行のしきい値なし直線仮説(LNT)にゆらぎが生じた」これに尽きるだろう。このことから,近年の保健物埋領域での議論をみると,先に述べた保健物理学の原点に帰った姿を見る思いがする。放射線リスクの捉え方の温度差放射線関係者間でも放射線リスクの提えかたには“温度差”が存在してギる。温度差の要因は,①情報に関するもの(放射線リスク論議に関する知識・情報の浸透度の違い),②放射線リスクに由来する利害の相違,また①②の複合したものも考えられる。講演者・コメンテー夕一の方々の講演内容,そして討論のなかでも発言内容にその温度差が感じられたが,立場の運いによる特徴があらわれていた。 “放射線は微量でも危険”という仮説で利益があるのは何もマスコミや環境原埋主義者やイデオロギー団体に限ったものではない。放射線リスクの取り決めには,科学的証拠・規制・認可・業務の独占・取り決め機構・社会的受容度等が関与する。そのほか放射線が“特別な存在”であることによって,「立場によって異なるリスクの大きさへの願望」の間題が入ってく るからである。放射線リスクの考え方や社会への適用の考え方が,属する立場によって変わってくるのは,いってみれば白然なことで,むしろ本能的である。だが,これが放射線リスク論議を複雑にしている要因でもあろう。 求められるわかりやすい放射線リスクの説明 放射線の有効利用という観点からも,一般市民への適切な放射線リスクの説明の開示は不可欠である。だが,社会にとって見える形の放射線リスクとは規制数値・措置であり,基本概念である放射線リスクの考え方や放射線防護の考え方は見えてこない。また,放射線のリスクの考え方と法的規制値は別物である。基本概念と規制のギャップをいかにわかりやすく説明するかこれからの保建物埋にはその知恵が求められているように感じられた。 (文中敬称略) 輪嶋隆博 (北梅道医療大学歯学部附属病院放射線部) Isotope News 1月号 2003年 |