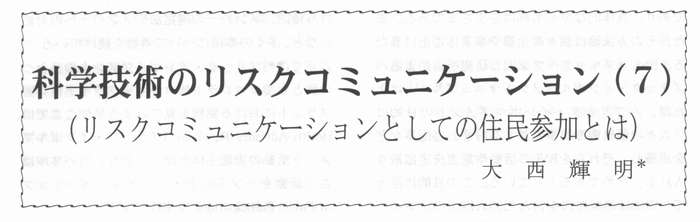 |
| 1.米国における住民参加:パブリック・インボルブメント 政策決定過程に人々の意見を取り入れようとする米国の試みは、1949年の「行政手続法」などから開始した。この法律によって住民の意見を行政に取り入れることが義務付けられたが、政策決定過程への積極的な住民の取り込みは、60〜70年代に始まる環境悪化問題への対処の一方策として考慮されてきた。この時代には地球資源の枯渇や人口増加による環境破壊、環境汚染などの諸問題が顕在化した。同時に、自然保護運動も活発化した結果、これに係る諸団体は専門集団化し、住民に直接関係した問題の取り組みには住民自らが関与するべきであるとして、環境に係る情報公開や住民参加を企業や事業体に強く要請するところとなった。 1970年施行の「国家環境政策法」(NEPA)では、環境問題の政策設定に係っては住民参加を制度として位置付けようとしたものである。 1976年のラブ・キャナル事件後には、スーパーファンド(Super Fund)法により企業や事業体に過去の環境汚染に対する修復義務を課し、さらに1984年のボパールの農薬漏洩事故をうけて、1986年10月には「緊急対処計画及び地域住民の知る権利法」により、企業や事業体に対して地域住民に環境負荷程度を知らせる義務を課した。また1990年施行の改訂クリーンエア法第112(r)条では、企業や事業体で最悪の事故が発生した場合のシナリオを想定し、それに基づいた管理計画を策定するとともに、そうしたリスク情報を地域住民に知らせることを義務付けてもいる。 こうした法制化の背景には、環境問題は良いか悪いかが明確に判断できるものであるため、環境面で住民や環境保護回体、消費者などに良いイメージを与える企業や事業体は、企業間の競争でより有利な位置に立てることが認識されてきたことによる。さらにこの延長として、自然破壊や汚染などの環境問題は、企業や事業体が地域住民や消費者と対立しては決して解決することはなく、両者が互いに相手の主張を聞き入れることが解決の第一歩であることも認識されてきたためである。すなわち、人々の関与のないところでなされた決定は、人々に反対されたりひっくり返されたりすることで失敗が多いが、人々の同意を得たり多くの関連ある人々の考えを含んだ状態での決定は長期間にわたって安定であることが、経験的にも明らかになったのである。これがパブリック・インボルブメントの考えであるが、こうしたパブリック・インボルブメントのためには様々なの手続き時間や経費がかかるが、計画終了段階ではそうしたことが時間的にも経済的にもかえって良い選択であったこと、地域社会から当該企業や事業体が良き隣人であるとの認知を受けることが事業の遂行にとっては極めて重要であること、多方面からの人々の意見を取り入れることによってより良い解決策を見出し得ることなどが、広く認識されるに至っている。 パブリック・インボルブメントは住民の知る権利や参加する権利の法的な保証の上に立ったものであり、具体的な型や名称はさまざまである。また、その方法論は個々の企業や事業体ごとに異なる。 BNL (ブルックヘブン国立研究所)によるパブリック・インボルブメントマニュアル(1)によれば、パブリック・インボルブメントの目的は「人々の価値観や物事に対する好悪、心配事などを認識し、それらをBNLの活動や意志決定に取り入れる」ためであるとしている。この目的に沿って、BNLは地域住民を含んだ30人以上のメンバーのBrookhaven Community Advisory Board を設け、これを介して住民の意見を聴取し、また人々の考えを反映する組織としている。こうしたことによる決定は直ちにインターネットweb、パンフレット、郵便物、新聞広告、CATVなどのメディアによって、人々にわかるレベルで広く情報公開すること、オープンハウスや技術デモなどによってBNLと地域との垣根を越え、人と人との関係を築くことを目指していること、それによってBNLと地域住民との相互理解と共通のグラウンドを築くべきことなどとしている。 現在、米国で定義するパブリック・インボルブメントはわが国で言うPAやPR活動形態をも含むが、これよりもさらに積極的に人々と接し、人々の意見を引き出すと言う意味合いを持つ。さらに、こうした従来型の手段や形態に加えて、住民自身が直接参加して彼等自身に係る事項の意志決定を行なおうとする活動をも含む、幅広いものをさす。従って、これはベースとなる考え方がリスクコミュニケーションとはやや異なるとは言うものの、その手段や方法はリスクコミュニケーションそのものに相当するといえる。 パブリック・インボルブメント活動の主体は上記の通り、通常CAPと略されるCommunity Advisory Panel,市民Advisory Group,市民パネル、Community Study Groupなど、様々な名称とスタイルを持つ。一般に、企業や事業体のこうしたパブリック・インボルブメント活動は、法的に評価されるところとなる。従って、企業や事業体はこの種の活動を効率よく進めるために相互に方法論を比較検討し、こうした組織の性格や責任範囲、付与権限、メンバーの選定法やメンバーヘの対処法など、多くの事項について考察を続けている(2)。以下ではパブリック・インボルブメントのひとつの例として、コロラド州ロッキーフラット核兵器プラントにおける実態を見てみよう(3)。ここでは、Health Advisory Pane1 がパブリック・インボルブメント活動の実施主体となっており、当パネルはこの活動をパブリック・パーティシペーション (Public Participation)と称している。 2.Health Advisory Panelによるパブリック・パーティシペーション活動 ロッキーフラット核兵器プラントから放射性物質が漏洩している事実が判明したのは、1969年の工場火災に際してであった。 1970〜80年代を通して世界的な反核運動が高揚し、ロッキーフラット汚染がメディアで報じられるたびに、工場周辺の住民の不安は高まった。特に1989年、当プラントが環境法を無視していると連邦規制局(Federal Bureau of lnstitution)に指摘されたため、この時期、人々の反対運動は最高潮に連した。コロラド州公衆衛生環境局は同プラントの汚染度の再調査(Dose Reconstruction Study)を行うこととし、1990年、科学者、医師、行政、一般市民などからなる12人のメンバーのHealth Advisory Pane1 を設け、当調査の委託業者からの報告を聴取し、それを住民へ説明することや、住民からの要望を聴取することなど任にあたらせることとした。 この汚染度再調査計画のフェーズ1はプラント操業の歴史的経過や事故歴などを調べ、1952年から89年の間に放射性物質や有害化学物質が事故時にどれほど漏洩したかや、人々の曝露確率や発ガンリスクなどを算出した。第2フェーズでは100人以上にわたるプラント従業員の聞き取りや非公開文書のチェック、環境モニターリングなどを実施して、さらに詳細なリスク分析を行った。この間、当パネルは次のようなパブリック・インボルブメント活動を行っている。 (1)住民集会や学習会:当パネルは4ヵ月に一度の割りで、2〜3日かけて技術調査報告会を開催し、調査委託業者が調査の進行状況を報告する場を設けている。これは昼間の一般公開であるが、これと同時に、パネルは夜間、前後24回にわたって住民集会を開催し、昼間の報告会の説明を行って、住民からの質問やコメントなどを聴取した。 住民集会開催のニュースは新聞やニュースレター、ダイレクトメールなどにより広報した。このため、毎回35〜125人の人たちが参加した。第1フェーズでは住民集会の他に、この問題について興味を持つ地元の人々や科学者、プラント従業員らが円卓会議を行い、さらに突っ込んだ議論も行った。第2フェーズでは集会の対象地域を広げて周辺の16市で行い、ゲストスピーカを招いてプルトニウムや白血病、ネバダ州核兵器実験場でのガン発生リスクなどについての話を人々に提供した。 一方、こうした技術報告会とは別に、これに先立って、パネルは調査委託業者や放射性物質火災の専門家、地域の人々などをメンバーとした学習会を開催し、過去のプラント火災事故の範囲や汚染程度の議論も行ってきた。また、1993年にはコロラド大学と共同で環境科学者、ジャーナリスト、学生、一般住民など200人以上の人々を集めて教育シンポジウム、Rocky Flats Health Risks: The Science behind the Issues を開催している。 (2)住民参加:パネルが作成するテクニカルレポートには住民の意見やコメント、専門家の批判などを入れることとした。住民集会で出された200件以上の疑問点や心配事などは、全てこのレポートで答えることとした。住民の多くは彼等の周辺ではどのような汚染状態となっているのかや、彼等の健康リスクはどうなのかを知りたがり、また、ともに調査を行うことも望んだ。 しかし、調査を担当する科学者が信頼の置ける人物であることがわかるとこうした関わりは疎遠となったため、特定の個人が長い期間にわたって継続して調査に関心を持ち続けたという住民の例はそれほど多くはない。住民がしだいに多く参加するにおよんで、調査の名称をHistorical Public Exposure Studiesと変え、学校敷地の汚染やプラント焼却場から排出されるダイオキシン、火災前後でのプルトニウムのマスバランスなどについても、調査範囲を広げた。 (3)出版:この問題に興味を持つ人々には最新の調査情報のほかに、集会予定などを載せた季刊のニュースレターを送付した。また、テクニカルレポートの市民用サマリーや、核施設からの健康リスク、被ばく経路、リスク評価の不確かさなどを話題とした技術トピックス、ファクトシートなども出版している。 (4)スピーカービューロ(Speaker' s Bureau):住民集会に出席しない市民やコミュニティーリーダに対しては、55のコミュニティーでスピーカービューロを設け、調査の目的や過程などを直接、解説した。パネルのメンバーはこの方法で、1500人以上に技術的内容も含めて説明している。 (5)インターネット・ウェブサイト: 調査ファクトシート、市民用サマリー、技術トピックスなど、45件以上をWebに掲載している。 (6)環境サンプリング市民委員会(Citizen ' sEnvironmenta1 Sampling Committee):放射性廃棄物処理場近くの住民は、行政の行う環境調査に強い不信感を持っていた。不信は、それがどれほど科学的に正確であるかとか、どれほど技術的に優れているかなどにはよらない。ロッキーフラットでは従来から、30件以上の土壌サンプリング調査がいくつもの行政体によって実施されてきたが、住民は行政体には不信であり、調査法や調査過程を疑問視していた。こうした不信感に答えるべく、1992年、この問題に興味を持つ住民グループや周辺地域のリーダ、地域の保健所の人々などを委員として、土壌のサンプリング調査委員会を設けた。パネルのメンバーは調査には介入せず、住民らが行う自主的な調査を見守るだけとした。この委員会は初めに、土壌調査の現場や大学の放射能測定室を見学し、その後、土壌中のプルトニウムレベルの調査を行うこととした。委員の中には時間の都合や調査速度と折り合わずドロップアウトする人も多く、出席率は必ずしも良くはなかった。しかし、ロッキーフラットの何箇所かで土壌採取し、また、比較のため飲料水を提供しているスタンドリー湖の堆積土なども調査し、これらでのプルトニウム測定値が従来、行政が発表してきた値と同じであることを確かめている。パネルはこうした結果のサマリーやレポートを作成し、住民集会で発表もしている。 (7)フオーカスグループ:調査が終盤に近づいたとき、パネルは地域住民や行政、興味を持つ市民グループなどからなるフオーカスグループ(中心的で、かつ人々の代表となり得るグループ)を組織し、プルトニウム漏洩の原因、リスクの不確かさ、プルトニウムの大気拡散などの、調査結果の技術的側面をどのように表現すれば最もよく人々に理解してもらえるかについて議論し、コメントを求めた。 (8)ビデオ:ローカルテレビ局、大学、公共図書館、住民団体などに、調査結果を解説したビデオを配布した。 (9)調査結果の広報:調査終了前には、パネルメンバーが直接、自治体の保健局や住民団体に調査結果を説明し、市民に広報するよう依頼した。1999年夏には記者会見や広報のためのオープンハウスを儲け、ここで写真や図なども展示した。市民はここへ来て展示をみ、技術者と直接会話し、ビィデオをみ、さらに印刷物を持ち帰ったりした。最終サマリーには調査の全過程、住民の被ばく過程、健康リスクなどを記述した。こうした結果はローカルメディアで公表し、また、専門書によっても公表した。 こうした住民広報およびパブリック・インボルブメント活動は、地域住民をロッキーフラットの調査に注目させ、過去の漏洩事故の再調査がいかに大変なものであるかを認識させる役目を果たした。パネルのメンバーは常に、住民が何を心配し、何を恐れているかについて配慮するとともに、リスクや不確実性などを人々が理解できるよう、7年間に亘って説明し続けてきた。こうして培った信頼感のおかげで、1999年の夏に結果が公表された時には、反対グループから批判の声があがることはなかった。 3.欧州における住民参加:コンセンサス会議 国民の代表者が集まり、与えられた科学技術を素人の立場から評価しようとする動きは、1980年代にデンマークから始まった。デンマークでは1987年以降、年間平均1件以上の割りで、大気汚染から遺伝子治療に至る幅広い分野でこうしたコンセンサス会議がもたれてきた。デンマークでの成功後、オランダ、イギリス、ニュージーランド、ノルウェー、オーストリア、フランス、スイス、オーストラリア、カナダ等もこの方式を取り入れ、人々の間で科学技術に対する議論を高め、人々自身が政策決定の一端に参加するシステムを作ってきた。 すでに前章で述べたとおり、この種の会議は通常、一般国民から選ばれた、当該事項には素人の人々が、技術的課題について専門家に質問し、専門家の回答を参考にして彼ら自身の価値観に沿った見解を導き、これを広く公表するという方式を取る。デンマーク技術委員会の採用したコンセンサス会議の過程は、以下のようなものである。 (1)8〜11人からなるアドバイザリー委員会を初めに組織する。この委員会は議題の設定、市民パネルの選定、招聘専門家の選定などを行う。 (2)委員会は市民パネルの質問に答える専門家のリストの作成を行う。 (3)委員会は次に、10〜20人の市民パネルメンバーを、メディアの広告募集によってか、または住民全体からランダムに抽出することで選定する。このとき、市民は当該問題に関しては素人であること、性、年齢、学歴、職業、居住地などに関して公平に選定することなどを条件とする。 (4)選定された市民パネルのメンバーは本会議以前に準備会合として何度か集合し、与えられた資料をもとに本会議で行う質問を考え、さらにそれに答えてほしい専門家を専門家リストから選出する。パネルのメンバーには準備会合から本会議を通してファシリテータが付き添い、発言やまとめの作成を手助ける。 (5)会議は招聘された専門家がパネルメンバーの出した質問に答え、それに対して議論を重ね、パネルメンバー自身が結論を出す。こうした結論を専門家のコメントとともに、レポートとしてまとめる。 こうした方法は専門家のみではなく、一般の人々も科学技術政策について発言権を持つことを保証するものであり、科学技術に対する判断を専門家のみにゆだねてはならないのではないかとする懐疑の念や、専門家への信頼感の喪失に根ざすところも小さくない。主として欧州でのコンセンサス会議は、最終的な意志決定段階よりも以前の段階で国民の意見を聞き、政策の変更可能性を保証しようとしていることや、こうした国民参加形態が政策決定過程のどの部分に、どれほどの権限で介入できるのかを明確に制度化しているところが特徴的である。以下では1998年、UKCEED (UK Center for Economic and Environmental Development)によって行われた、放射性廃棄物に関する英国ナショナルコンセンサス会議を例として紹介しよう(4)。 4.UKCEEDによる1998年の放射生廃棄物に関するコンセンサス会議 現代社会では一般の人々と政治や政治家との距離があまりにも大きく乖離し過ぎているとの反省から、英国政府は人々の政策決定への係わりを大きくすることによって民主性の欠如した部分を補おうとしてきた。市民パネルや市民陪審員制度はこうしたものの現われであり、コンセンサス会議もまたこうしたものの1例である。 英国での第1回ナショナルコンセンサス会議は1994年、バイオ技術を議題として開催され、1998年のこれは第2回目となる。第1回会議のパネルメンバーは多くの点でバイオ技術の開発推進を留保しようとする提案をなしたが、実際の政策決定でこうした提案がかえりみられることはなかったといってもよい。しかし、1994年の提案をもっと真剣に受け入れていたならば、今日の遺伝子組み替え食品に関する諸問題も、幾分かは緩和できたのではないかとする指摘も多い。 第2回のこの会議では、まず全国の選挙人名簿から4000人を無作為に抽出し、この人々に会議の議題は知らせずに出席の意向を打診した。約120人が参加を希望したので、この人々には議題(中高レベル放射性廃棄物を長い時間にわたって有効に管理するにはどうすればよいか)を知らせ、2度にわたる準備会合と4日間にわたる本会議への参加意向を再度、確認した。このうち約70人が興味を示し、参加を希望したので、この中から16人をランダムに選出し、最終的には15人が本会議のメンバーとなった。 専門家については200人以上の候補者に打診したが、このうち約80人が参加を表明した。市民パネルメンバーは本会議の2ケ月前の週末に開催された第1回準備会合で、こうして選定された専門家のリストを渡され、第2回準備会合の最後に、この中からメンバーの質問に答えるための専門家26人を選出した。 本会議は4日間にわたったが、最初の2日間は9セッションに分かれ、約1時間半の各セッションごとに市民パネルが出した質問の一つひとつを検討した。このとき、専門家は一人あたり5分の説明を行い、その後、専門家とパネルメンバーとの間で討論を行った。この2日間は公開であるが、第3日は非公開とし、パネルメンバーはそれまでに得た知識と2日間の議論をもとに結論と提案を検討した。第4日日はこれらの結論と提案が一般公衆やメディアに公開され、これに対して政府や産業界、環境保護グループ代表者などがコメントを加えて終了した。今回のパネルメンバーが提出した質問は、以下の9項目である。 (1)放射性廃棄物の深地層、浅地層処分のそれぞれの利点はなにか (2)放射性廃棄物を作り出しているBNFL以外の機関がそれを管理するという政策は取れないのか (3)現在、放射性廃棄物処理に関してどのような研究がなされているのか (4)原子力の民営化は放射性廃棄物の一括管理を困難にするのではないか。現在の安全基準が、民営化によって緩められることはないのか (5)放射性廃棄物に関して人々にどのように広報しようとしているのか (6)使用済み核燃料を再処理のために輸入することで、我々にはどんなメリットがあるのか (7)原子力を続けることに対するあなたの意見は? その経済的、社会的コストについてはどう考えるのか (8)解体した原子力潜水艦はどうするのか。軍事基地でなくなったとされる放射性廃棄物については、現在どんな調査が行われているのか (9)高レベルや中レベルなどの、放射性廃棄物の区分表記についてはどう考えるか パネルメンバーは質問(1)を、まず最初の質問とすることに全会一致している。質問(1)について、最終報告をさらに詳しく見てみよう。 パネルメンバー全員の意見は、もしも将来なんらかの利用策が見つかれば我々の子孫がそれを取り出せるように、放射性廃棄物は人々がアクセスでき、モニターできる場所に保存しておくべきであると言う点では一致していた。メンバーは、放射性廃棄物処分の事業主体であるNIREXが、最終処分を保留すべきであるとする専門家の意見を聞く姿勢にあることを評価しはするものの、まだ、NIREXは深地層処分にこだわっているとする印象を持ったとしている。さらに、NIREX自体が公衆に対して不信感を抱いていることをメンバーは心配し、NIREXまたはその後続機関は今後、政策的にオープンであり、人々と常にコンタクトを保つべきであるとしている。こうした機関は産業界や科学界、環境グループや一般市民などからなる独立した組織の管理のもとに置かれるべきであり、放射性廃棄物処分場の選定にあたっては、こうした組織と政府とが共同してオープンな計画のもとで行うべきであることや、廃棄(disposal)や埋設(burial)と言う言葉は誤解を招きやすいので、貯蔵(storage)と言い換えるほうがよいこと、地上での保管は環境変化や人間による様々な妨害などの心配があるので地下貯蔵とするべきこと、地下貯蔵はバックフイルで満たされた地中処分(deep isposal)ではなく、将来の人々がそれを利用し得る可能性を残したものとするべきこと、さらに、現在の原子力発電所跡地を保管地として利用する可能性を検討するべきことなどを、パネルメンバーは最終報告書で提案している。 これに対して例えば環境大臣は、将来の気候変動や地殻変動の可能性を考えた場合、処分した放射性廃棄物の環境安全性を保証するためには深地層処分とすべきであるが、パネルの提案する浅地層貯蔵についても、今後は考慮すべき選択肢となりうるとしている。また、NIREXとは独立した中立組織がNIREXを管理するべきだとすることには賛成するが、大量の放射性物質の貯蔵地をどこにするかは技術だけではなく社会学の問題でもあり、たとえオープンではあっても、それを政治的に決めるのは大変危険であるなどとコメントしている。 一方NIREXは、放射性廃棄物の再利用可能な場所での貯蔵という考えにはNIREXも同意し、それを選択肢とする方向に政策を変更しつつあると述べ、また、地上での保管からしだいに地下貯蔵に移行するべきであることや、深地層処分が最終的な解決策であると信じてはいるが、こうした移行には注意を払い、状況が変われば他の方法での処分に変更できるよう、可逆的な措置とするよう検討していることなどをコメントしている。 このような住民参加形態が単なる手続きや形式に終わることなく、政策的に有効に機能することが望まれるところである。この場合、常に問題となるのは以下のような事柄についてであろう。 (1)議論の内容が専門家や全市民、全国民に広く行き渡るシステムとなっているのか (2)専門家パネル、および市民パネルは、それぞれ専門家や市民をどれほど正しく代表するものであるのか (3)市民パネルからの提案がどのように政策に反映されるのか。すなわち、こうした住民参加形態は、科学技術政策上の意思決定過程のどの部分に、どのような権限を有するものなのかなどであろう。こうした点に注意しつつ、以下ではわが国の場合について見てみよう。 5.わが国における住民参加型リスクコミュニケーション 従来からのわが国での住民参加の例としては、公開ヒアリング制度をあげることができよう。しかし、これは単なる行政処理過程上での手続きであるにすぎず、公開ヒアリングの開催時点では既に政策は決定してしまい、計画の変更や修正を可能とするものではない。既に見てきたように、近年の欧米の住民参加プログラムは単なる情報公開ではなく、それが意思決定過程と必然的に結びついているが、わが国の公開ヒアリングは説明や同意を求めるための1過程に過ぎないともいえよう。 米国では既に1944年、「行政手続法」によって住民の意見を聴取することを行政に義務付けているが、これに相当する法制度がわが国で成立したのは1999年3月、閣議決定によってであった。これは「『規制の制定または改廃』の際の意見提出手続」、いわゆる「パブリックコメント」法であり、この法の成立後、様々な行政機関や自治体がこの法に従って、政策の立案・決定過程で政策のあり方や政策案に対する住民の意見を(例えば、インターネットを介して)聴取し、それを考慮して政策作りを進めるということが行われ始めている。 住民の意見を聴取するためには、それに係る情報の公開が前提となる。わが国での「情報公開法」は1999年5月に成立したが、この後、49都道府県全てで「情報公開条例」が作られた。これにより法的には、人々が企業や事業体にとっては不利となるリスク情報の開示を要求することが可能となった。また、同年7月には「環境汚染物質排出・移動登録法」(PRTR法)も成立し、企業や事業体に対して彼等が環境に排出する有害化学物質の種類と量とを政府に報告し、これを開示する義務を課した。 しかし、こうした排出物質がどれほど、人々や環境に対してリスクを及ぼしているかについては報告の義務はなく、また、万一の事故時の緊急事態下では、最大どれほどのリスクを及ぼすことになるのかなどについても公開する義務を課してはいない。 いわゆる「円卓会議」は、もうひとつの住民参加形態であると言えよう。これは成田空港問題の紛争解決にある程度の効果があったことから、1990年代に入って、環境問題や公共事業問題に係って次第に各地で採用されてきた方式である。例えば、千葉県京葉臨海地域に沿って広がる東京湾の三番瀬埋め立て問題では、学識経験者9名、地元住民3名、地元漁民4名、地元経済界代表者1名、環境保護グループ代表者4名、公募によって選出した一般市民3名の計24名のメンバーから成る三番瀬再生計両検討会議が、2002年以降、円卓会議の形式で開催されている。こうした円卓会議は現在までに、千歳川流域治水対策検討委員会、愛知万博検討会議、長良川河口堰に関する円卓会議、淀川水系流域委員会など、10件ほどが実施されている。 上記の三番瀬は東京湾の北縁辺部に位置する干湯浅海岸であり、1960年代初頭に埋め立て計画が策定されていた。 しかし、地域住民や環境保護運動グループはこれに強く反対し、また、環境保護意識の高揚とも相侯って、千葉県は1999年に埋め立て計画の縮小を発表していた。この円卓会議の設置は2001年、堂本知事による三番瀬埋め立て計画中止の決定に端を発したものであり、三番瀬の再生計画を県民自身が参加し、進めるために、2002年1月に設置されたものである(5)。ここでは従来の検討会議に見られるような、国や自治体が原案を作り、それを委員が審議するというスタイルではなく、参加者が専門家の知識や行政の力を借りると言えども、参加者自身が自らの地の再生計画を策定するというものであった。 したがって、こうした理念に係っては欧州のコンセンサス会議にも匹敵するものと言えよう。当円卓会議ではその会議の組織化の準備段階から完全公開の方針を貫いており、委員は公募により選出し、会議や会議議事録の公開なども積極的に行っている。また、当会議の目的は三番瀬の再生計画を住民参加によって作成し、それを知事に提案することであるとしているが、提案そのものを計画として決定する権限はこの会議には付与されてはいない。当検討会議のもとには護岸・陸域、海域および制度の3小委員会を設け、これらの小委員会のもとにさらに7つのワーキンググループを設けている。これらとは別に専門家会議も設置し、委員会やワーキング・グループヘの助言などを行っている。2004年1月までに22回の円卓会議を含め163回の会議を開催し、三番瀬の自然再生のための具体的施索やラムサール条約への登録促進などに関する提案を提出して終了している(6)。 一方、千歳川流域治水対策検討委員会は次のような状況である(7)。すなわち、1982年、建設省は北海道石狩川の洪水対策としての放水路建設に着目し、その支流である千歳川の水流を太平洋に放流するための千歳川放水路計画を決定している。この直後から、石狩川流域や放水路予定ルート周辺の自治体、農協、漁協、商工組合、自然保護団体、市民団体などは賛否入り乱れ、長期にわたり推進、反対運動を繰り広げてきた。こうした状況下にあって1997年9月、堀達也知事は千歳川放水路問題の膠着状態を打開するために、知事の私的諮問機関として7名の委員からなる円卓会議、千歳川流域治水対策検討委員会を設置し、「地域の合意としての治水対策」の提案を行わせることとした。この検討委の呼びかけに応じて、放水路建設に賛成、または反対する関係主要団体の代表者7名と、行政からの2名のオブザーバー、および7名の検討委員会委員からなる計16名の拡大会議を併設した。これら二つの会議を総称して、円卓会議と呼んでいる。 1年以上にわたるこれら会議の設置期間中、検討委は23回、拡大会議は16回に渡りほとんど交互に開催され、互いに相補的な議論や検討を行ってきている。 1999年2月に検討委は「中間まとめ」を行い、それに対する各団体からの意見を参考にして、最終的な提言を同年6月に行っている。この提言では、千歳川および石狩川の合流点を含めた流域における総合治水対策を推進するべきだとしながらも、千歳川放水路計画については検討の対象としないとしている。これを受けて知事は同年8月、千歳川放水路計画の中止を決定している。この円卓会議は各方面の利害関係者を含むものであり、関係者の意見を徹底的に聞くと言う、陪審制度的性格を持つものであった。円卓会議で「まとめ」としての結論が出すことができたのは、“これで結論が出なければ膠着状態がさらに延々と続き、肝心の治水対策が進展しないのではないかとする共通の危機感が背景にあっだとも分析されている(7)。 こうした例以外にも、2002年2月に設けられた国土交通省近畿地方整備局による55名の委員からなる淀川水系流域委員会でも、会議や会議議事録の公開、委員や意見の公募など、全面的な情報公開や住民参加方式を取り入れている。このように近年の河川流域整備や海浜開発などの公共事業では、従来型合意形成方式の不成功の反省の上に立ち、旧来の諸問題の仕切り直しに際しては、最終的な意志決定過程以前に、住民参加による住民自身の意思表示によって政策やその方向性を決めようとする動きが全国的に見られるようになってきた。これは、1997年の改正河川法によって地域住民の意見を反映させることや、同年成立の「環境影響評価法」によって、公共事業のアセスメントには一般の人々や環境保護諸団体からの意見を聴取すべきことなどが要請されたことにもよる。 しかし、こうした住民参加方式が、長年にわたって未解決状態が続いてきた紛争事項を解決に導くことができることを実証したという点では、極めて注目すべき事柄であろう。 (1)”Community Involvement Plan”, BNL-52562(1999) (2)E.PeeUe,“Citizen Advisory Groups: Improving Their effectiveness”,USDOE Rep. CONF-9008119(1990),pp.45-62 (3) N.C.Morin and A.J.Lockhart,”Public Involvement in a Dose Reconstruction Study: The Colorado Story”, Proc.10th Int.Cong.Int.Rad.Prot.Assoc.,(Hiroshima,2000),P-10-153 (4)http://www.ukceed.or/consensus-conference/ ’UK CEED Consensus Conference on Radioactive Waste” (5)千葉県土木部河川海岸課、「三番瀬円卓会議について」、海岸、42(2002)、92−94 (6)三番瀬再生計画検討会議、「三番瀬再生計画案」(2004年1月22日) (7)山田家正、「円卓会議が果たした役割と提言in「市民が止めた! 千歳川放水路一公共事業を変える道すじ−」(日本野鳥の会等編、北海道新聞社、2003)、pp.175 |